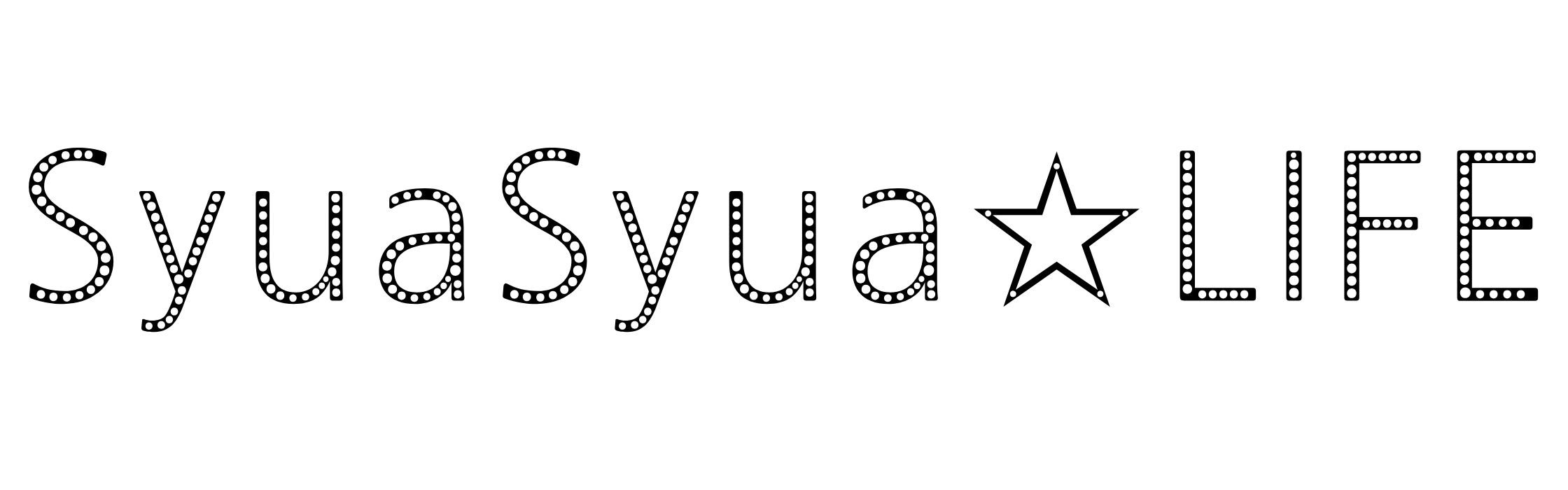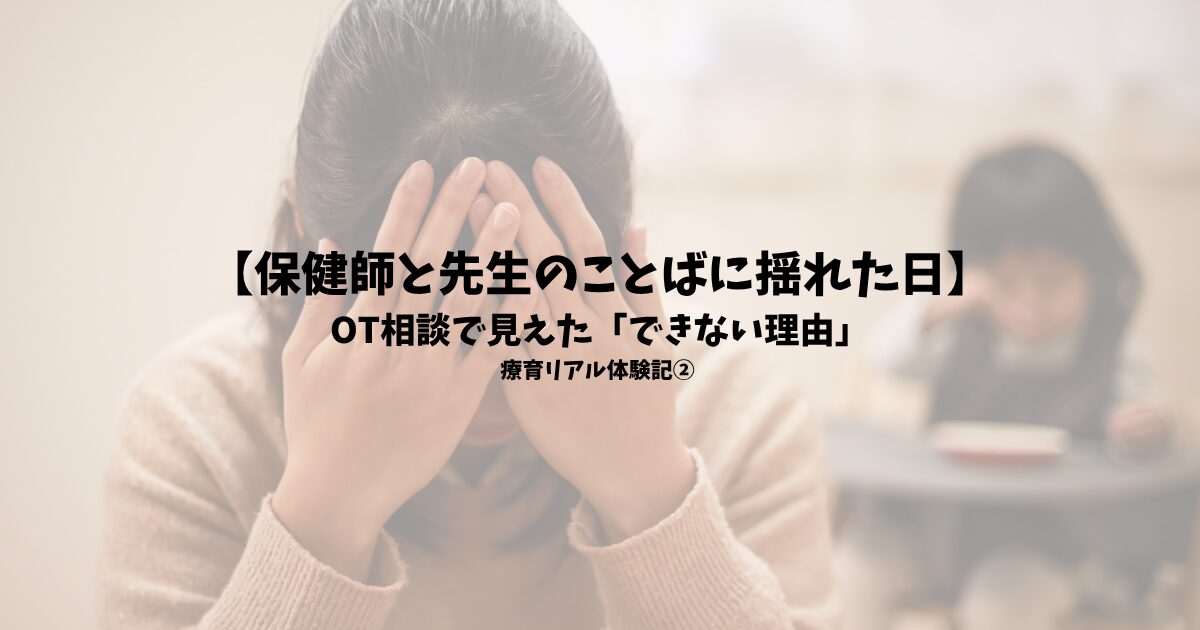【支援級か普通級か】初めて突きつけられた選択|療育リアル体験記③
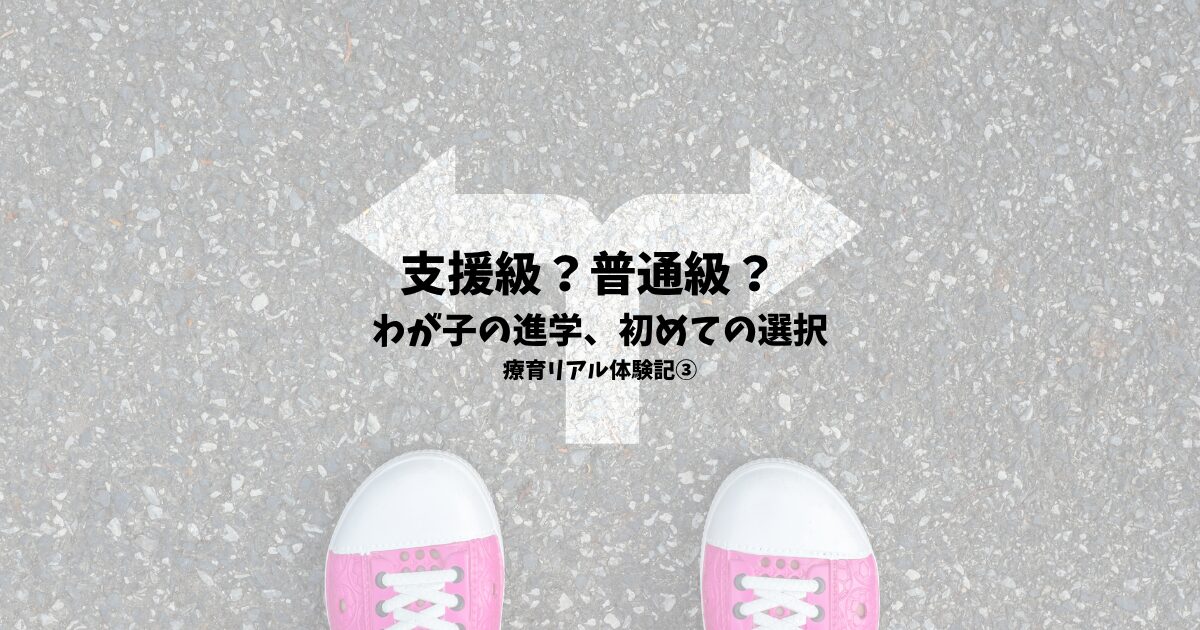
小学校進学/支援級の悩み
療育に通い始めて半年ほど経った、年長の6月。
ある日、療育支援の主催で「進級に向けた懇談会」が開催されるという案内が届きました。
講師としていらしていたのは、支援級の先生を経験され、現在は放課後デイサービスを運営されているベテランの先生。
「進級について、現場のリアルな話が聞けるはず!」と、私は少し緊張しながらも期待を抱いて参加しました。
支援学校に行くかもしれない?
しかし、懇談会の冒頭で先生がこうおっしゃったのです。
「この懇談会に参加されている保護者の皆さんは、まずご自分のお子様が支援学校に進学する可能性がある、ということを認識してください。」
その言葉を聞いた瞬間、胸がギュッと締めつけられるような気持ちになりました。
「うちの子が支援学校に行くかもしれない…?」
息子は0歳から保育園に通い、少人数の同級生たちと日々を共にしてきました。
そのみんなと同じように小学校に進学するものだと、どこかで信じて疑わなかった私。
けれど、先生の一言でその“当たり前”が崩れていくような感覚がありました。
「少し成長がゆっくりなだけ」と思っていた息子が、“特別な支援”を必要とする子であるという現実を、初めて突きつけられた気がしました。
進学の振り分けと選択
懇談会では、その後に支援級・支援学校についての制度的な説明が行われました。
大まかな流れは、以下のようなものでした。
- 教育委員会による進路の振り分け(通常級・支援級・支援学校)
- 保護者に意向確認と、不服申し立てがある場合は面談・話し合いへ
- 最終的な進学先の決定
この流れを踏まえ、我が家でも発達検査を受け、先生や教育委員会との面談を経て、「支援級での進学」が決定しました。
支援級での進学と心の揺れ
当時、息子は授業中にじっと座っていられない様子があり、「やはり支援級の方が安心して学べるかもしれない」と私自身も感じていました。
だからこそ、不服申し立てはせず、そのまま支援級での進学を選びました。
でも、懇談会のあの先生の言葉は、帰り道の車の中でもずっと胸に引っかかっていて…。
運転しながら、涙がこぼれそうになるのを必死に堪えたことを今でもよく覚えています。
支援級3年目の今、思うこと
あれから月日は流れ、息子は支援級での学校生活をスタートし、現在は3年生になりました。
最初の授業参観のとき、支援級の教室で静かに授業を受けている息子の様子を見ながら、ふと隣の教室から聞こえてくる元気な音読の声に、少し寂しさを感じました。
「お友達と一緒に本を読む、そんな時間をうちの子は過ごせないのかな…」
でも、国語・算数では1学年ほど遅れている息子にとって、支援級の環境は「自分のペースで安心して学べる場所」になっています。
理解に時間がかかる息子でも、少しずつ、でも確実に前に進んでいます。
そして今では、「支援級を選んで本当によかった」と心から思えるようになりました。