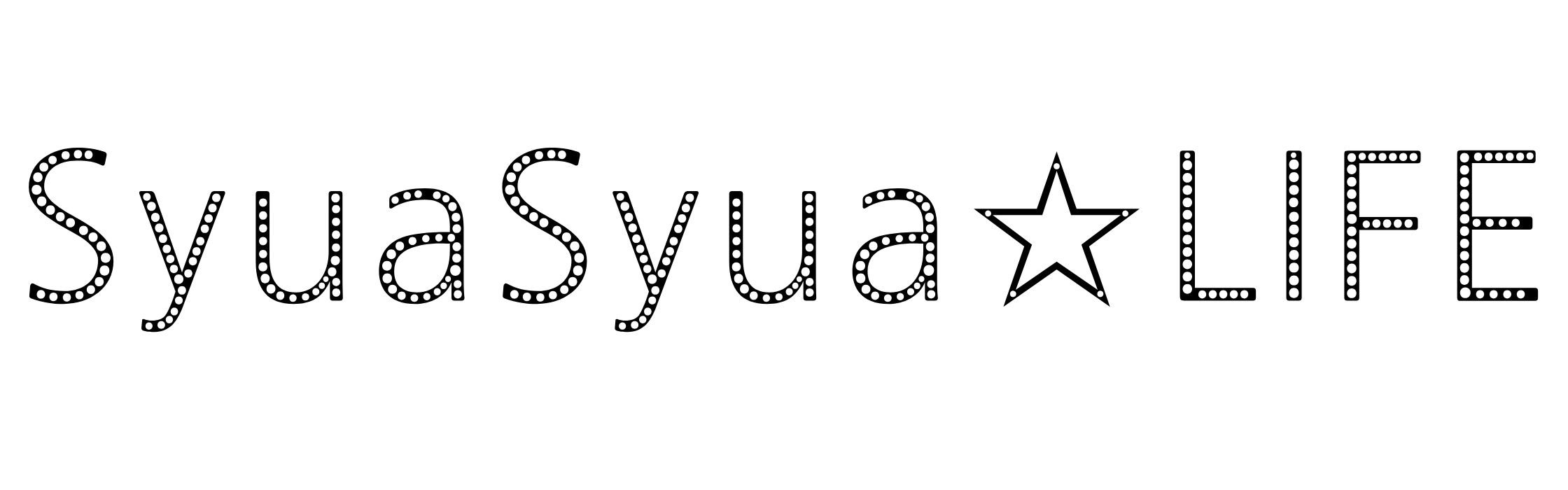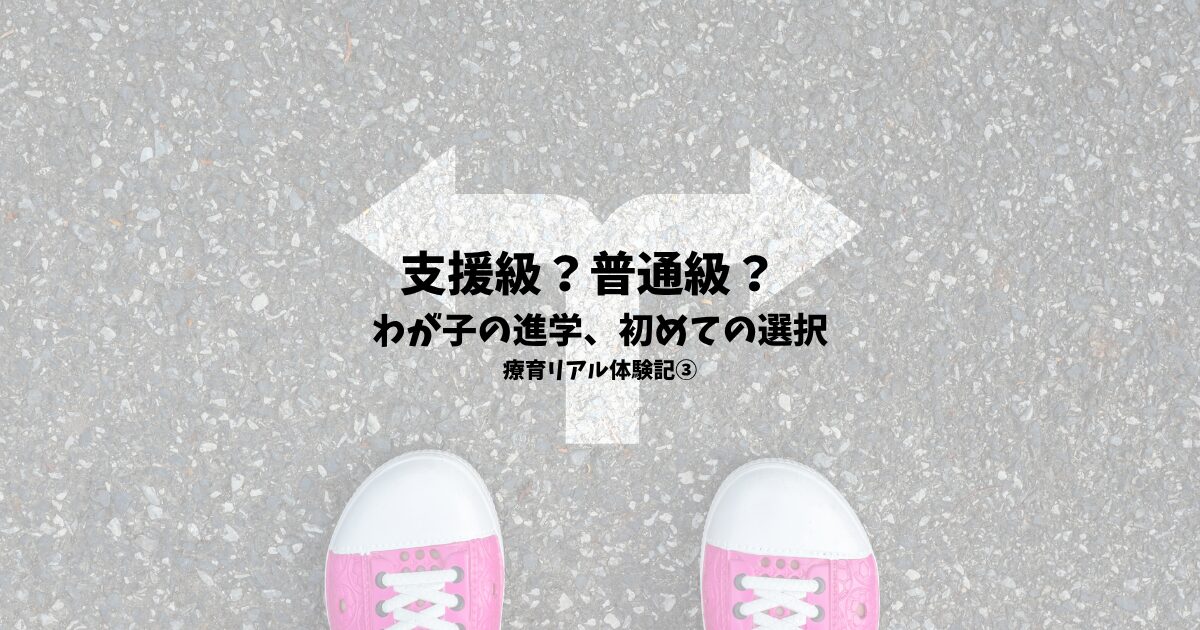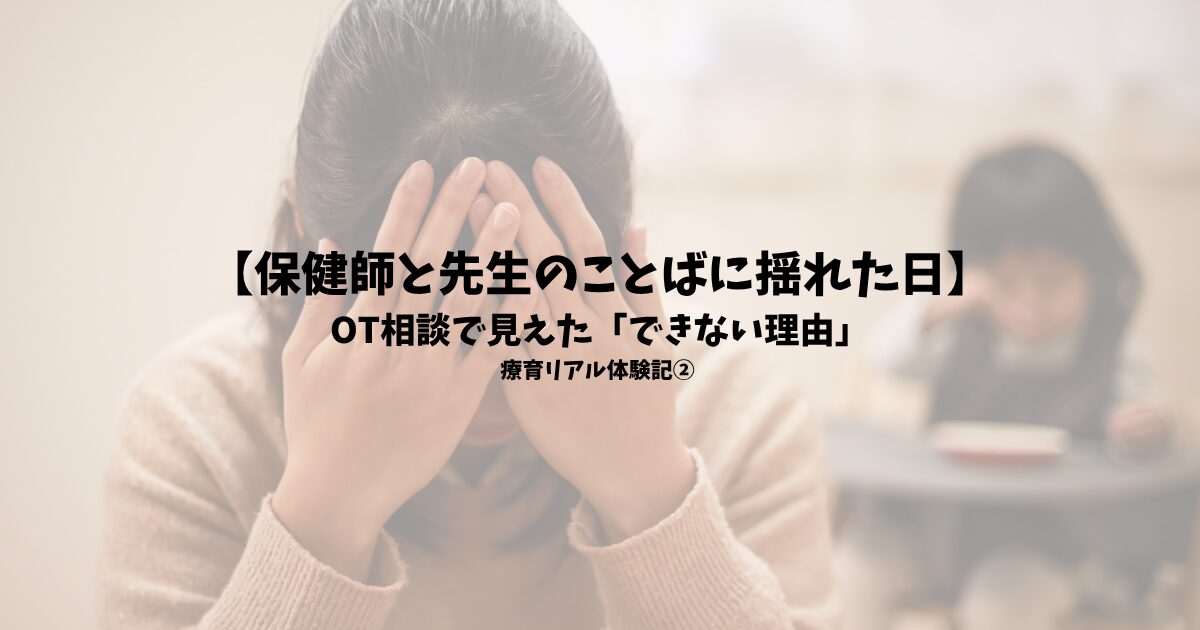発達障害って診断されるまでの、もやもやと不安の毎日~わたし一人だけじゃなかった~

はじめに|誰にも言えなかった気持ち
今まで、誰にも話せなかったけれど……
同じように悩んでいるママがいたら、少しでも気持ちが楽になってほしくて。
そんな思いで、このブログを書いています。
一人目の育児でママ一年生だった私は、
「療育ってなに?」「うちの子って障害なの?」「グレーってどういう意味?」
──そんな疑問だらけの毎日でした。
しかも、田舎暮らしで同級生は10人ほど。
療育に通っているのは息子だけ。
【悩み】周囲に同じようなママがいない。相談する人がいない。
→ 結果、検索魔になる。でも、正解はわからない…
悩んでいるのに誰にも言えず、
モヤモヤした気持ちを抱えたまま、どんどん心が疲れていきました。
「なんか、みんなと違う?」最初の違和感
息子が2歳になるちょっと前、ようやく歩き出しました。
市の健診で引っかかり、小児科の先生に見てもらうと…
この子は、歩く必要を感じてないんだよ
「???」と驚きましたが、今では笑える思い出です。
周囲と比べて気づいたこと
3歳を過ぎた頃。
他の子がスッと帰れるのに、息子はなかなか来ない。
気づけば、いつも最後に園を出るのはうちの子でした。
それでも当時の私は、
まぁ、小さいし、遊びたいだけかな
気のせいだよね
と、無理やり納得しようとしていました。
「育て方が悪いのかな…」と悩んだ日々
発達障害の知識なんてなかった私は、
周囲に相談しても、こう返されることがほとんどでした。
💬「そんなのどこも一緒だよ!」
💬「大丈夫、大丈夫!」
今思えば、励まそうとしてくれていたのだと思います。
でも、当時の私は…
やっぱり私の育て方が悪いのかな…
と、どんどん自信を失っていきました。
診断までの道のり|癇癪、過呼吸、療育…
2歳:健診→OT(作業療法)の個別相談へ
3歳:癇癪、過呼吸が頻発 → 医療機関の受診・療育スタート
【ポイント】
相談の第一歩は「気になることを話してみる」こと。
小さな違和感でも、専門の方に聞いてみるとスッと道が開けることもあります。
支援級へ進学。伝えるという選択
小学校では支援級に進学することに。
そのとき、私は思い切って保護者の皆さんにこう伝えました。
🗣「息子は支援級でお世話になります。
もし、お子さんが“〇〇くんはどうして?”と聞いてきたら、
ご家庭で話していただけると助かります。」
結果、周囲に気を遣わせることなく、自然にスタートを切ることができました。
傷ついた言葉。それでも前へ
あるママに、こんなふうに言われました。
私だったら、そんなの分かった時点で普通にやっていける自信ないわ〜
悪気がないのは分かっていたけれど、胸が締めつけられました。
(私だって、そんな自信なかったよ!)
でも、あの日を越えて、私は少しずつ強くなっていきました。
今|「親の余裕が、子どもの安心」
息子は今、小学3年生。
癇癪もなくなり、落ち着いて学校生活を送れています。
先生に言われた言葉
「成長しない子はいません」
→ 今なら、心からその言葉を信じられます。
そして私もようやく、「親の余裕」が子どもの安心につながるんだと気づけました。
同じように悩むママさんへ
「なんか違うかも…?」と感じたその気持ち。
それは、母親の“本能”かもしれません。
【大事なこと】
・気になったら相談する
・早く知れば、子どもが生きやすくなる
・診断されなくても、相談するだけでラクになる
うちの子も、支援級という選択肢があったからこそ、
自分らしく毎日を送れています。
おわりに|わたしもここにいます
ここまで読んでくださり、ありがとうございます。
このブログが、誰かひとりの心に届いてくれたら嬉しいです。
🌸「一人じゃないよ。わたしもここにいるよ」
▶️次回予告
次回は、実際に療育を受けはじめた日々のリアルについて書いていきます。
療育で変わったこと、ママとして得た気づきなど、赤裸々にお届けしますね!